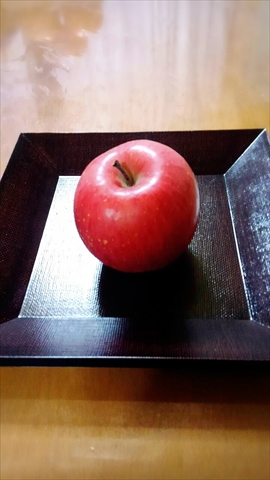 稽古
稽古 且座
前回茶道の「七」について話しましたが忘れていた「七」がありました。千家七事式です。 ・花月の式・且座(さざ)の式・一二三(いちにさん)の式・数茶(かずちゃ)の式・茶カブキの式・廻り花 / 花寄せ・廻り炭 七事式の中で、以前茶カブキと廻り炭と...
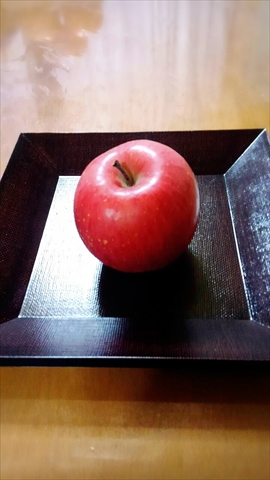 稽古
稽古  茶道雑記
茶道雑記  茶道雑記
茶道雑記 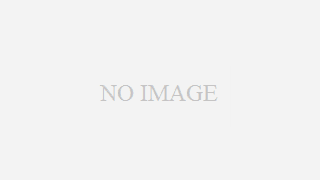 展示会
展示会  稽古
稽古  稽古
稽古  稽古
稽古